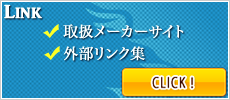Blogページ - 美容総合商社-株式会社マックス-
今、話題の炭酸美容について
こんにちはマックスIT委員会です。 今回は”炭酸ミスト””炭酸泉シャンプー・ヘッドスパ”などで注目を集めている「炭酸美容」についてお話します。 医療現場や美容業界で注目されている「炭酸」。その起源は天然の炭酸温泉、ヨーロッパでは”心臓の湯”と呼ばれ、ドイツでは温泉地が多く皮膚病や健康促進のためのクアハウス(療養センター)もあります。 炭酸泉の効果としては、血液の循環がよくなる、動脈硬化や心臓病などの循環器疾患の症状の緩和、冷え性・高血圧・肩こり・血行障害の改善などが挙げられます。 肌が炭酸水に触れることで血の巡りがよくなる。肌から入り込んだ炭酸(二酸化炭素)を老廃物(異物)と認識した体が、排出 ・・・
マックス全体会議
こんにちは,マックスIT委員会です。 今回は4/21に阿倍野区民センターで行なわれた第35期MCS全体会議をレポートします。 まず去年から営業配属になった吉田康治くんの理念唱和!!引き締まります。 続いて綱瀬社長の方針発表。今期のマックスの方向性を示します!!2012年のスローガン”自ら創る自分になろう 自ら創る会社になろう” 次にディスカッション。日本一のトヨタ代理店トヨタネッツ南国のビデオ鑑賞しグループで当社に取り入れたい活動をグループで発表! 昼食を挟み社員1人ずつ今期の決意表明。営業一年目の岡田くんも気合い入ってます。 2011年年間表彰・売上達成 ・・・
『にわか仕込み』 ― 長いお付き合いについて考える ―
仕込むは色々な意味を持ちます。 ①主に酒・醤油・味噌・ワインなど 発酵させて長期間熟成させるものを、混ぜて醸造するための処置をすることがひとつの意味です。 ②刀をさやに収めるといった具合に、中に作り入れることも仕込むと表現します。 座頭市が使っていた仕込み杖は、刀を仕込んであるから仕込み杖っていうのですね。 ③さらに、商人が商品を仕入れたり、飲食店が材料を買い入れて営業の準備をしたりすることも、仕込むって表現をします。 ④そして、現在一番頻繁に使用されるものが、『芸を仕込む』といったように、教え込んで訓練する意味です。 この④は、①の熟成して育てること+②の作り込んで準備すること+③の先行投資 ・・・
IT委員会発足!!
こんにちは株式会社マックスの西岡です。 春を迎え桜満開のなか新たな第35期がスタートし、2週間経ちました。 当社では人事発表、組織改編が発表され、4/21に行う当社全体会議に向け各個人・各チームが行動プラン、抱負などの資料作成に勤しんでおります。その中で今期は 新たに!! なんと!! IT委員会が発足!!しました!! facebookは各個人で行い、マックスページは社長含め管理者が更新するのですが、 現状のホームページ 4月からのこのブログ を充実させ、お客様に価値のある情報にする為発足されました。 メンバー紹介!!まずは私、西岡大悟 ブログも初めて、facebookも本格始動は今年からですが ・・・
北村美容研究会
今日は北村美容研究会の当社が事務局を務める大阪支部のアップスタイルセミナー。 北村賢会長・・・2008年6月、北村美容研究会会長就任。2009年8月株式会社女性モード社より「魅せるアップデザイン」を出版。コンテスターとして優勝、入賞など多数の受賞歴をもつ。 北村美容研究会とは1967年に北村龍彦名誉会長により ◇美容技術を通じて、「共に楽しく学び育つ姿勢」を重視した活動 ◇セット・アップ・フィニッシングの技術を追求する ◇ 研究を深める為、セットと関連するカット・カラー・パーマの技術を追求 ◇ 美容技術の伝承 ◆ サロン、スタッフ、業界の発展と繁栄 ◆ 美容業技術、知識、感性の向上 ◆ 美容師 ・・・